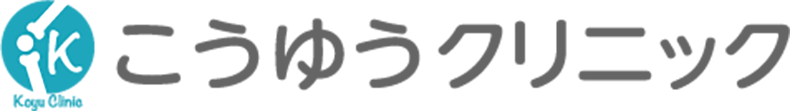骨粗しょう症
骨粗しょう症について
骨粗しょう症とは
骨粗しょう症とは何らかの原因で骨が弱くなる病気です。
その結果、転倒やしりもちなどで手首や腰の骨、脚の骨の骨折がみられます。
ご高齢の方ではそのまま寝たきりになる方も多くいらっしゃいます。
骨粗しょう症の方の骨折で多い、脚付け根(大腿骨近位部骨折)の骨折では骨折後の1年間の死亡率が10パーセントととても危険な骨折です。
骨粗しょう症は早めに診断、早くからの治療がとても重要です。

なりやすい人は
骨粗しょう症は様々な原因で起こりえます。
男性にもなりますが、特に女性に多い病気です。
女性は女性ホルモンの影響が強く、50歳以上の女性では3人に1人が骨粗鬆症です。
また、下記に当てはまる方なども骨粗しょう症になりやすいと言われています。
- ご両親が骨粗しょう症の人やご両親が脚の骨を骨折したことがある方
- ご自身が何らかのご病気でステロイドのお薬を使用している方
- 糖尿病や腎臓が悪いと言われている方
- 痩せている方
- タバコをよく吸う方
- アルコールをよく飲む方
“毎年健康診断を受けていて、特に問題ない”と言われている方でも、骨密度を検査したことがある方、また、定期的に検査している方は少ないと思います。
骨粗しょう症は何もしなければ進行します。そして、骨折すると寝たきりになる可能性が多いとても怖い病気です。
まずはご自身の骨の強さ(骨密度)を知ることが重要です。
ご自身の今後10年以内に骨粗しょう症による骨折するリスクを計算できます(FRAX)
骨密度検査とは
当院の骨密度検査は腰と大腿骨の骨の強さを測るDEXA法を導入しています。
この方法は微量なX線をあてることで、骨折しやすい腰と大腿骨の骨の強さを正確に測定することができます。
検査はベッドの上に寝て頂くだけで、所要時間は5~10分程度で終了します。
特に予約などは必要なく、検査が空いていればすぐに検査ができます。
骨密度検査で骨粗鬆症と診断された場合、今後の治療方針選択のため採血をさせて頂くことがあります。

骨密度検査の費用
骨密度検査のみ実施した場合の費用は以下になります。
| 初診の方 | |
|---|---|
| 1割負担の方 | 740円 |
| 2割負担の方 | 1,480円 |
| 3割負担の方 | 2,210円 |
| 再診の方 | |
|---|---|
| 1割負担の方 | 520円 |
| 2割負担の方 | 1,050円 |
| 3割負担の方 | 1,570円 |
治療
骨粗しょう症の治療では食事や運動は重要となります。
骨を作るのに重要なビタミンDやカルシウムを積極的に摂取して頂くことや、日光を浴びて、運動をすることが大切です。
その上で、骨粗しょう症と診断をされたらお薬を使用し骨がこれ以上弱くならないように、そして少しずつでも強くすることが大事です。
お薬には飲み薬や注射など様々なお薬があります。
「飲み薬をこれ以上増やしたくない」、「注射はちょっといやだ」、「忘れちゃうから週1回の薬がいい」「月に1回の薬がいい」などご本人のライフスタイルに合わせてお薬を検討させて頂きます。
骨粗しょう症の治療はすぐに効果がでるものではなく、日々の食生活や運動とお薬を使うことでゆっくりと治療することが重要です。